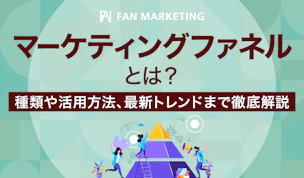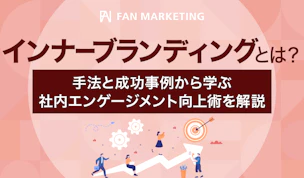ユーザーコミュニティのメリットとは?成功させるためのポイントや作り方
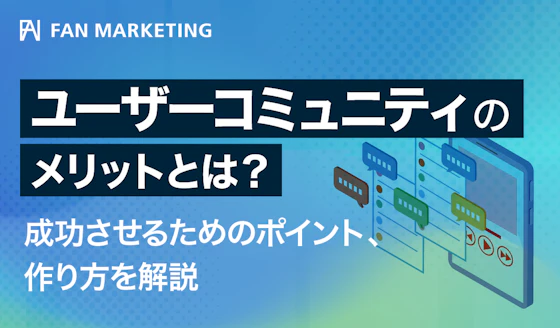
国内の人口減少、ものやサービスの飽和により、競合他社との差別化がますます難しくなっています。そんななか、ユーザーとのつながりを深めてファン化を促進する「ユーザーコミュニティ」が注目されています。ユーザーコミュニティを活用することで、顧客ニーズの把握や商品・サービスの改善、カスタマーサポートのコスト削減、そしてLTV(顧客生涯価値)の向上といった大きなメリットが期待できます。今回はユーザーコミュニティを作るメリットや成功事例、作り方、ポイントなどについて、ファン育成のプロである株式会社ファン・マーケティングが分かりやすく解説します。
- ユーザーコミュニティの立ち上げを検討している企業様
- 顧客とコミュニケーションを増やしたい企業様
- ユーザーコミュニティとは何か、いまいちよく分からない方
ユーザーコミュニティとは?
ユーザーコミュニティとは、利用している製品やサービスについてユーザー同士で交流する場・集まりのことです。現在はネット上での交流が主流で、具体的には、誰でもコメントを投稿できる掲示板やQ&Aコーナーなどが例として挙げられます。また、交流のみではなく、企業がサイト内でイベントを企画したり、コンテンツを発信したりすることもあり、ユーザーコミュニティを用いたマーケティングは「コミュニティマーケティング」とも呼ばれます。
これを聞くと、SNSとは何が違うのかと疑問に思った方もいるのではないでしょうか?SNSとの大きな違いは、企業とユーザー同士のコミュニケーションの密度です。一方向の情報発信にとどまりやすいSNSに対し、ユーザーコミュニティではユーザー同士、または企業とユーザーの双方向で、交流を継続的に深めやすいという特徴があります。
また、ユーザーコミュニティが発展している背景として、インターネットやSNSの発達が挙げられます。特にSNSが普及したことで、ユーザー自身が気軽に情報発信を行えるようになり、さまざまな情報が出回るようになりました。
株式会社ホットリンクの調査によると、1年間のうちにネット上の口コミ情報を参考に、商品を購入したことのある人は約86%に上るといわれています。※つまり、さまざまな情報があふれるなかで、相対的に企業とユーザーの接点が持ちにくくなっているといえます。だからこそ、ある程度企業側が統制しながらユーザーと双方向なコミュニケーションをとり、中長期的な関係を築くことができるユーザーコミュニティが注目されているのです。
ユーザーコミュニティのメリット3つ
ユーザーコミュニティを活用すると、企業はさまざまなメリットを得られます。ユーザーと交流する機会が生まれることで、顧客と共に新しい価値を作り出せるのも大きなメリットの1つです。また、ユーザー同士でそれぞれの問題を解決できる場合もあるため、カスタマーサポートのコスト削減も期待できます。さらに、企業やサービスのファンを増やせるというメリットもあり、中長期的に見て企業の成長につながります。ここではそれぞれのメリットについて詳しく解説します。
- 顧客と共に新たな価値を作り出せる
- カスタマーサポートのコストを削減できる
- 企業・サービスのファンとなるユーザーを増やせる
顧客と共に新たな価値を作り出せる
1番のメリットとして、ユーザーコミュニティを通して顧客からアイデアを募ったり、意見を聞いたりすることで、顧客ニーズを的確に把握しやすくなることがあります。たとえば、社内では当たり前だと思っていたことが顧客にとっては大きな価値であったり、社内で気付けなかった改善点が見つかったりします。このように、ユーザーコミュニティという双方向のコミュニケーションができる場を通して、ニーズを的確にくみ取り、効率的かつ効果的に商品の改良を行いやすくなるでしょう。さらに、企業側だけでは気付けないような、ユーザーならではの視点を得ることで、さらに新しい製品やサービスの創造につながることもあるのです。
カスタマーサポートのコストを削減できる
ユーザー同士で商品に対する疑問に回答し合ったり、それに関するアイデアを出し合ったりという交流により、コミュニティ内で問題が解決する場合もあるため、カスタマーサポートのコスト削減が期待できます。また、このことは企業だけではなく消費者にとっても、いつでも好きなときに気軽に疑問を投げかけられ、場合によっては早期に問題解決できるというメリットも生まれます。

企業・サービスのファンとなるユーザーを増やせる
ユーザーコミュニティを活用することで、企業やそのサービス・製品のファンを増やし、中長期的に利用し続けてもらえるようになるというメリットが生じます。ユーザーコミュニティを通し、商品やサービスを共通の話題として交流を繰り返すことで、ユーザー同士で一体感が生まれ企業への愛着や信頼感の向上が期待できるためです。なお、企業への愛着を持ったファンとなるユーザーを増やすことは以下のような理由、背景から重要であると考えられます。
口コミ力の向上
ファンとなるユーザーは、周りの人に商品やサービスのよさを広めてくれる傾向にあり、宣伝効果も見込めます。企業が宣伝をするよりも、第三者であるユーザーからの評価のほうが信頼性が高いと感じる人も少なくないため、新規顧客の獲得にもつながりやすいといった大きなメリットが生まれます。
新規獲得の難化
少子高齢化・他企業との差別化の難化といった市場変化に伴い、新規顧客の獲得はさらに難しくなると予測されています。そのため、ユーザーと中長期的な関係を築き、LTV(顧客生涯価値)を高めることは重要性を増しているといえます。LTVとは、顧客が、ある企業と取引を始めてから終了するまでに、どれくらいの利益をもたらしてくれるのかを表したものです。
パレートの法則
パレートの法則とは、企業利益の8割は、サービス・商品の利用者全体のうち2割の利用者が生み出すとされている法則のことです。その2割は、定期的に企業のサービス・商品を購入してくれるファンであり、そのようなユーザーを育成するために、ユーザーコミュニティは有効な手段の1つとなっています。
1:5の法則
1:5の法則とは、新規の顧客を獲得するには、既存の顧客を獲得し続けるコストの5倍かかるという法則です。パレートの法則からも、企業が安定して利益を出していくためには新規顧客を獲得するだけでなく、ファンとなる既存顧客と中長期的な関係を築くことも重視されています。
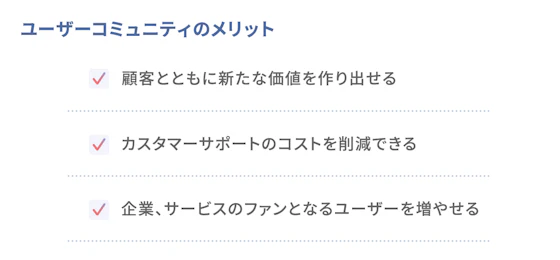
ユーザーコミュニティを活用することで、顧客ニーズの把握やコスト削減、ファンの獲得といったメリットを得ることができます。株式会社ファン・マーケティングでは、企画立案からコミュニティサイトの構築・運営支援まで一貫して対応しています。自社に合ったユーザーコミュニティを作りたい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
ユーザーコミュニティの成功事例
ユーザーコミュニティは具体的にどのような企業が実践し、どのような交流があるのでしょうか?次に、ユーザーコミュニティの成功事例をご紹介します。
- Salesforceの学びの場「Trailblazer Community」
- カインズのDIYコミュニティ「Cainz DIY Square」
- 富士通のICTユーザ会「Fujitsu ユーザーコミュニティ」
- 大和ハウス工業のつながりの場「ダイワファミリークラブ」
Salesforceの学びの場「Trailblazer Community」
クラウド型のアプリケーションを提供するSalesforceでは、ユーザーから管理者、開発者までの人が集まる、「Trailblazer Community」というユーザーコミュニティがあります。2025年8月現在、Trailblazer Communityでは19個のコミュニティグループが存在し、イベントが月に10回以上もあるなど、活発な交流の輪が広がっていることが分かります。このような場を通して、ユーザー同士で、最新機能の使い方や活用事例などについての情報共有が行われているのです。このように、ユーザーコミュニティという場で分からないことを解消したり、よりよい活用方法を教え合ったりすることで製品を長く効果的に使ってもらえることから、ユーザーコミュニティの成功事例だといえるでしょう。

カインズのDIYコミュニティ「Cainz DIY Square」
大手ホームセンターの会社であるカインズには、DIYを楽しむ人たちが集まるユーザーコミュニティ、「Cainz DIY Square」というものがあります。このコミュニティでは、DIYをライフスタイルとして発展させることを目的として、ユーザー同士でDIY作品を共有したり、DIYのアドバイスを受けたりできます。
さらに、初心者でも安心なDIYのワークショップも開催されたり、活動状況に応じたポイント付与制度も導入されたりしており、さまざまな工夫がなされていることが分かります。そのため、企業にとってメリットがあるだけでなく、消費者にとっても自分が作ったDIY作品を披露する場になったり、技術のレベルアップを目指せたりというメリットも多くあるのです。また、DIY作品の投稿に対して月間20万~30万件もの「いいね」が付くユーザーも存在しており、ユーザーの多さや活動の活発さから、ユーザーコミュニティの成功事例としてよく取り上げられています。

富士通のICTユーザ会「Fujitsu ユーザーコミュニティ」
ICT業界のリーディングカンパニーである富士通は、ビジネスパートナー企業や団体を対象とした国内最大級のユーザーコミュニティ「Fujitsuユーザーコミュニティ」を運営しています。このコミュニティは、北海道から沖縄までの全国11支部と、LS研究委員会によって構成されており、地理的な垣根を越えて会員同士がつながり合い、ICTを活用した実践的な課題解決や価値創出に取り組んでいます。
さらに、AI・イノベーション・物流・人事・経営など、業種横断でテーマ別に設けられた分科会では、富士通と会員企業が協力して知見を深め合うことが可能です。また、Fujitsuユーザーコミュニティは情報共有と人材育成の場としても非常に充実しており、オンラインコンテンツや、人材育成プログラムなど、デジタル人材の成長を支援する仕組みも整備されています。このように、「Fujitsuユーザーコミュニティ」は単なる交流の場ではなく、ICTを通じて新しい価値を共創し、地域・社会の発展にも貢献するプラットフォームとして、ユーザーコミュニティの理想形を体現しているといえるでしょう。

【自社事例】大和ハウス工業のつながりの場「ダイワファミリークラブ」
大和ハウス工業が運営する「ダイワファミリークラブ」は、同社の住宅オーナー様専用の会員サイトで、住まいや暮らしをサポートするためのさまざまな情報と交流の場を提供しています。2001年の開設以来、会員数は10万人を超え、メンテナンス情報や暮らしを豊かにするライフスタイルのアドバイス、大和ハウスグループの優待特典など、役立つコンテンツが充実しているユーザーコミュニティです。
また、オーナー同士で質問やアドバイスを交わす「オーナーズQ&A」や自由に会話できる「おしゃべりパーク」など、住まいに関する実体験や気付きを共有するコミュニティ機能も持ち、会員間のつながりを強化しています。さらに、住宅履歴や長期修繕計画など各種管理機能もそろっており、オーナーの安心かつ継続的な暮らしの支援と、企業と顧客との長期的な信頼関係構築を実現している点が大きな特長です。

大和ハウス工業様とともに、「ダイワファミリークラブ」をリニューアルしたのが、ファン育成のプロである株式会社ファン・マーケティングです。ファンマーケティングの知見を活かし、既存オーナー様との長期的な関係構築の場としてのユーザーコミュニティの構築を実現いたしました。「顧客との関係を深め、ファンを増やしたい」「LTVを高めたい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
ユーザーコミュニティの作り方
ユーザーコミュニティを構築する際には、まずターゲットと目的を決めます。その後、企画の大枠を決定し、企画を実現するためのツールを選定します。ツールを用いて自社のコンセプトに合ったコミュニティサイトを作成しましょう。そして、企画やイベントの詳細を決定し、実行することで、交流の活発化を促すことがポイントです。最後に、企画後のユーザーの反応を分析したり、悪質なユーザーがいないか確認したりしながら、ユーザーコミュニティを運用します。
- ターゲットと目的を決める
- 企画の大枠を決める
- ツールを選定する
- コミュニティサイトを作る
- 企画の詳細を詰め、実行する
- 運用する
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。

1.ターゲットと目的を決める
まずは自社の製品やサービスを、誰がどのように愛用しているのか、どのような人がファンとなってくれそうかを検討しておきましょう。たとえばカインズのDIYコミュニティのターゲットには、DIYの質問を気軽にしたいユーザーや、居住地の問題から対面型のワークショップに参加できないといった悩みを持つユーザーが含まれています。
また、何のためにユーザーコミュニティを作りたいのかを明確にしましょう。目的や、それを達成するためのコンセプトも決めておくことで軸がぶれず、コミュニティの存続につながりやすくなるのです。加えて、コンセプトを統一することで、似た価値観を持つユーザーが集まりやすくなり、コミュニティが活性化しやすくなることもあります。
2.企画の大枠を決める
ユーザーコミュニティで何をどのようにやりたいかをざっくり考えましょう。たとえば、ユーザー同士で話せる掲示板を作る、セミナー・ウェビナーを定期的に開くといったイベントなどが挙げられます。ここで考えた構想が次のステップのツール選びの基準となります。
3.ツールを選定する
次に、前のステップで決めた大枠の企画をもとに、その企画を実現できそうなツールを選定します。ツールがあれば、プログラミングの専門的な知識や技術がなくても、ユーザーコミュニティの基本的な機能を備えたサイトを作成できます。
4.コミュニティサイトを作る
ツールはあくまでもテンプレートなので、テンプレートを使ってそれぞれのコンセプトや目的に沿ったサイトを作っていきましょう。どのようなビジュアルにするかは、ユーザーが抱く印象を大きく左右するだけでなく、使いやすさにも影響します。そのため、UI・UXの知識があるデザイナーの手を使って制作するのが理想です。
また、これらはユーザーの興味を引くサイトになるかどうかを決める重要な作業の1つです。長期的に使用する土台となるため、ツールの選択やサイトの作成が難しいと感じる場合は、ユーザーコミュニティサービスを提供している会社に委託するのも方法の1つとなります。
5.企画の詳細を詰め、実施する
コミュニティサイトが完成したら、交流を活発にさせるための企画やイベントの詳細を詰めて、いざ実行します。その際ポイントになるのが、ユーザーへの周知です。新しい企画やイベントの開催を、メールやSNSを通して周知するといったように、ユーザーコミュニティに来訪してもらう仕掛け作りも重要となります。
6.運用する
コミュニティ構築後は悪質なユーザーがいないかを監視したり、企画後のユーザーの反応を分析したりしてユーザーコミュニティを運営します。ユーザーコミュニティを成功させるにはこの段階が一番難しく、極めて重要なものとなります。

「企画はあるけど具体化できない」「ツール選びや設計に自信がない」「運営のリソースが足りない」といったお悩みをお持ちの企業様は、株式会社ファン・マーケティングにぜひ一度ご相談ください。これまで培ってきた経験を活かして、企業様のお悩みに合わせてサポートいたします。
ユーザーコミュニティの注意点
ユーザーコミュニティを運営する際は、継続的にリソースが必要になったり、ユーザーがすぐに離脱してしまったりと、構築後の運営が難しいという点に注意しましょう。また、収益化には時間がかかり、短期的な利益追求はユーザーの離脱を招くため、長期的な視点でKPIを設定することが大切です。さらに、ツールの導入だけでは不十分で、運営体制や企画を自社で整備し、十分に準備してから進める必要があります。
構築後の運営が難しい.
ユーザーコミュニティでは、炎上しないように投稿を定期的に監視したり、ユーザーを飽きさせないようなイベントを定期的に開催したりと、運営にある程度の時間や人手といったリソースを確保する必要があります。また、十分な人手やリソースを確保し、そのような運営を行っていたとしても企画とニーズが合っていなければユーザーを引き付けられず人が集まらなかったり、すぐに離脱してしまったりすることもあります。
そのため、大手企業であっても人手が集まらず、コミュニティを作っても運営の難しさから断念することもあるのです。こういった点から、ユーザーコミュニティを構築するときは、自社で行わず、知見があるほかの会社に委託するのがおすすめです。その際には、どこまで運用を代行してくれるのか、改善のための提案をしてくれるのかなど、サポート体制の充実度を確認しておくとよいでしょう。
収益となるまで時間がかかる
短期的にユーザーコミュニティ内で利益を上げようとするとユーザーが離れやすくなる傾向があります。たとえば、企業からの宣伝色が強いと、ユーザーは売りつけられていると感じ、コミュニティにいる価値を失い、離脱してしまいます。また、ユーザーコミュニティの効果を数値化して客観的に分析しにくいことも注意点として挙げられるため、アクティブユーザー数やコメント数といったKPIを設けることも必要となるでしょう。
ツールを導入するのみでは不十分
先ほども述べたように、ツールはあくまでテンプレートであるため、デザインを自ら手がけ、企画を練る必要があります。さらに、サイト構築後の運営は難易度が高いため、ツールをどのように利用するのか、運営体制をどのようにして整えるのかを事前に決め入念に準備することが必要不可欠です。

ユーザーコミュニティは「作って終わり」ではなく、効果的に運用するために、戦略的かつ継続的な運営力が求められます。また、社内に十分な人的リソースや専門知識がない場合、自社で完結させようとすると企画倒れや早期の離脱につながってしまうケースも少なくありません。そのような課題に直面しないためには、初期設計から運用まで一貫して伴走できるパートナーの存在が重要です。
株式会社ファン・マーケティングでは、ユーザーコミュニティの構築からその後の運用まで、ワンストップでサポートしています。「社内で進めきれずに困っている」「形にしたいがどこから始めればいいかわからない」という企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
ユーザーコミュニティの運営を成功させるポイント4つ
ユーザーコミュニティを成功させるためにはサイトを構築し企画を立てるだけでなく、その後の運営が結果を左右する鍵といえます。ユーザーの活動環境を整えたり、当事者意識を持たせたりすることで、ユーザーコミュニティによって顧客ロイヤルティの向上が見込めるでしょう。また、交流の場以外にも付加価値を持たせれば、ユーザーの離脱を防ぐことも大切です。しかし、成功させるポイントを抑えていても、ユーザーコミュニティの運用は困難なため、プロによる代行も検討しましょう。

ユーザー同士が安心して活動できる環境を整える
運営する際には、ユーザー同士が安心して快適に交流・活動できる環境となるよう努めましょう。コミュニティ内で誹謗中傷や悪質なコメントを投稿するユーザーへの対応ができていないと、トラブルにつながったり、ほかの良質なユーザーが離脱したりすることにもなりかねません。そのため、悪質なユーザーがいないか定期的に監視することも良質なユーザーコミュニティを作る手段の1つです。また、監視する以外に、コミュニティの状況に応じてルールやガイドラインを設置することも有効な対策です。
ユーザーに当事者意識を持たせる
ユーザーが受け身になりにくいテーマを発信したり、イベントに参加してもらったりすることでユーザーに当事者意識を持たせましょう。当事者意識を持ってもらうことでさらに交流が活発化したり、離脱率が低下したりすることが期待できます。また、当事者意識を持ってもらうために、コミュニティ内で積極的に活動しているユーザーに特典を与えることも手段の1つです。さらに、コミュニティメンバーの声やアイデアを商品や企業の企画に取り入れるといったことも、顧客ロイヤルティの向上に効果的でしょう。
交流の場以外の付加価値を提供する
ユーザーが交流するだけではなく、その製品やサービスに関する付加価値を提供することで、ファンとなるユーザーを獲得しやすくなり、離脱の防止につながります。たとえば、会員限定でクーポンを配布するといったことはユーザーにとって魅力的な特典といえます。また、企業側からコミュニティ限定の情報やコンテンツを発信してユーザーを楽しませることも付加価値の1つです。
プロに代行してもらう
ユーザーコミュニティについて知見があるプロに運用を代行してもらったり、コンサルティングしてもらったりするのがおすすめです。運営にリソースをあまり割けない、ユーザーコミュニティの作り方がよく分からないという方は、依頼を検討してみるとよいでしょう。
株式会社ファン・マーケティングでは、企画から運営、サポートまでワンストップで行っています。企画の段階から客観的な視点を混ぜながらユーザーコミュニティを作成するとより効果的なものとなります。ぜひ一度ご相談ください。
よくある質問
ここではユーザーコミュニティに関するよくある質問にお答えします。
コミュニティツールとは?
コミュニティツールとは、企業が顧客やユーザー同士の交流の場をオンライン上に構築・管理し、ユーザー満足度の向上やロイヤル顧客の育成を目的とするツールです。プログラミングの専門知識がなくても、コミュニティツールを活用することで、コミュニティサイトの構築や運営ができます。代表的なコミュニティツールは以下の通りです。
コミュニティツール | 特徴 |
|---|---|
QON | AIを活用した独自技術と専門的なサポートで企業のファンコミュニティを戦略的に構築・活性化するコミュニティツール |
coorum | ノーコードで自由度の高いUI/UXのコミュニティを簡単に構築でき、顧客単位での行動・声のデータ収集と分析を活用してロイヤルカスタマー育成やLTV最大化を実現できるツール |
Commune | 顧客ポータルやコミュニティを簡単に構築・運用でき、データ分析やKPI設計など運営支援が強みであるコミュニティツール |
OSIRO | デザイン性と機能性を両立し、企業とファンが深くつながるコミュニティを効率的に運営できるコミュニティツール |
コミュニティツールを用いてユーザーコミュニティを自社で構築・運営することも可能ですが、より質の高い運営を求めるならマーケティング会社への依頼が効果的です。株式会社ファン・マーケティングでは、スクラッチ開発によるコミュニティ運営や既存ツールを使った企画・運営支援を行っています。ユーザーコミュニティの構築・運営についてお困りの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
●株式会社ファン・マーケティングへのご相談はこちら
ユーザーコミュニティの運用は難しい?
コミュニティ運用は難しいとされる理由は主に以下の3点です。
- 成果の定量化が困難なため運営の評価がしにくい
- 継続的に新しい企画やイベントを行う必要がある
- 運営管理を怠るとユーザー間のトラブルが起こる可能性がある
ユーザーコミュニティによる直接的な売上やCV(コンバージョン)を測りにくく、運用施策の効果を客観的に評価しにくい側面があります。さらに、ユーザーの関心を引き続けるには、新しい企画やイベント、コンテンツを定期的に発信する必要があり、運営リソースの確保が必要です。また、炎上や荒らしといったリスクに常に備える必要があり、投稿監視やガイドライン整備など、地道な運用体制が求められます。
ユーザーコミュニティの運用は、難しいといわれることも多いですが、うまく活用できると企業のファン育成につながる施策の1つです。ユーザーコミュニティの運用に不安がある企業様は、ぜひ一度株式会社ファン・マーケティングにご相談ください。これまで企業様のファン育成をサポートしてきた豊富な経験を活かして、安心して運用できるようサポートいたします。
ユーザーコミュニティの企画・運用は株式会社ファン・マーケティングにお任せください
ここまでユーザーコミュニティの概要やメリットから作り方、運営方法などについて解説してきました。企業にとって、LTVの向上やファン化といった大きなメリットがある一方で、サイトの構築や運営が難しい側面もあります。
デジタルマーケティングを通したファン作りに特化している株式会社ファン・マーケティングでは、ユーザーコミュニティの企画、構築からその後の運用まで一貫してサポートを行っています。コミュニティサイトのデザインから構築後の監視業務、企画の分析・改善までお任せください。
企画の段階では、ニーズや理想像を丁寧にヒアリングし、ユーザーコミュニティをお客様と共に作り上げます。そしてコミュニティ構築後は、ユーザーコミュニティに関するこれまでの知見を生かし、独自の監視体制やガイドラインを活用し、徹底的なサポートを行っております。また、抽選商品を用いたキャンペーンも、商品の選定から発送までワンストップで承っているので、まずはお気軽にご相談ください。
※出典:株式会社ホットリンク,「インターネット上のクチコミを参考に8割超が商品を購入。購入商品のTOP3は、食品・化粧品・日用雑貨」(最終閲覧日: 2025年9月10日)